がん語らいの交差点 わたしのがんカフェ
星野史雄のパラメディカWeb書店

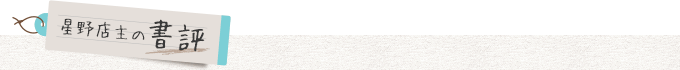
「脱病院化社会 医療の限界」(イヴァン・イリッチ/晶文社・1998年)という本がある。店主が闘病記さがしを開始して二、三年経った頃、医学史や医療倫理に関する本も集め始めた。現代を“病院化社会”というならば、患者は多くの恩恵を今の医療システムから蒙っている。しかし、“医原病”という言葉があるように、治療するはずが、却って新たな“病”を生み出すこともある。
そこで手にしたのが、大田区にある「昭和のくらし博物館」館長の小泉和子さんの労作「家で病気を治した時代」だ。この本には戦前・戦後の家庭看護に用いられた道具の図版が多く掲載されている。昭和27年生まれの店主には珍しいものばかりだ。例えば14ページ、昭和20年代までは自宅出産が一般的だったと言うが、産婆や家族が準備したものの写真が掲げられている。「闘病」という言葉は、実は「肺結核」の時代に生まれたものなのだが、この本に感想を書き始めると止まらなくなりそうなので、この本から連想した“コント”と関連する闘病記を紹介して、パラメディカらしい書評とさせていただく。
1961年から1972年まで続いた日本テレビのバラエティー「シャボン玉ホリデー」を覚えていらっしゃる方もおいでだろう。
病気で寝ている父親(ハナ肇)の枕元へ娘たち(ザ・ピーナッツ)がやってくる。
娘たち「おとっつぁん、お粥が出来たわよ。」
父「いつもすまないねぇー。こんな時、おっかさんが生きていてくれたらなぁ。」
娘たち「それは言わない約束でしょ。」
そこへ植木等が登場し、ひっかきまわすと「お呼びでない?こりゃまた失礼しました。」
と言い、全員ずっこける、というのがパターンだった。
クレージー・キャッツのリーダーだったハナ肇(野々山定夫)は1993年に肝細胞がんのため63歳で亡くなるのだが、亡くなったのは杏林大学付属病院の病室で、自宅の畳の上ではなかった。だが、病室を訪ねるザ・ピーナッツは「おとっつぁん」とコントを始め、ハナも「いつもすまないねぇー」と受けていたという。
ハナ肇さんの闘病記は奥様が書かれた「幸せだったねハナちゃん」(野々山葉子/扶桑社・1994年)と、付き人だったなべおさみの「病室のシャボン玉ホリデー ハナ肇、最期の29日間」(2008年/文藝春秋)の二冊がある。