がん語らいの交差点 わたしのがんカフェ
星野史雄のパラメディカWeb書店

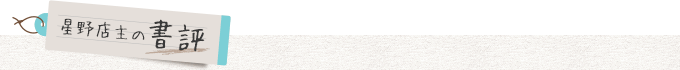
2008年に整形外科医である著者の父が、末期の肺がんと診断されてから亡くなるまでの三ヶ月間を綴る。著者の頭にはずっと「患者」と「医師」二種類が存在していたが、高齢の父ががんと分かって以来、「患者の家族」という立場が存在することを身にしみて感じたという。がん治療に専門外の著者は、先ず父の治療に一般の抗がん剤点滴を選ぶか、飲み薬のイレッサを選ぶか、選択を迫られる。娘として、一方で医師として、考えたことは...。
皆さんこんにちは。店員の山田です。 今回も素晴らしい闘病記を紹介できることを幸せに思います。紹介するのは「生命の羅針盤」。執筆者の山田恵子さんは整形外科医で、自分の父親が肺がんになりました。その発覚から父親が亡くなられるまで、さらにその後までの記録です。
山田さんの父親は高齢ではあるものの、タバコも吸わず、生真面目に仕事をする人でした。しかし、突然のがん告知。そして、高齢にも関わらず、がんが非常に早く進行していきます。患者本人はもちろん、家族も、次々と決断を迫られます。治療の段階では、複数ある治療法のどちらを選ぶのか。その次は積極的治療を続けるのか、ターミナルケアに切り替えるのか。そして、看取りの場所は病院か、自宅か。
今、医療の主人公が医師から患者へと移ってきています。おかげで患者はより自分らしい治療、自分らしい予後を送ることができるようになりました。告知もなくいきなり抗癌剤を投与されていた頃とは、比較にならないほどの進歩です。しかし一方で、患者はかつてのように「じっと寝ていればいい」状態から、様々な決断を自分でしなければならないストレスにさらされることになりました。
この本の素晴らしいところは、著者である山田さんが、常に「医師としての自分」と「娘(家族)としての自分」を分けて執筆していることです。「医師としてはこのように判断するが、娘としてはこうしてあげたい」。全てはこのように二人分の視点で書かれています。家族が書いた闘病記も医療者が書いた闘病記もたくさんありますが、この本はその両方がそろっています。読んでいると、まるで、医療の専門家に自分のそばにいてもらって、闘病記を読みながら、わからないところを教えてもらっている感じ。非常に分かりやすいです。
ちょっと話が変わりますが、私は先日、がん治療後では最大の腰痛に襲われました。もともと腰痛持ちなのですが、今回は右足のしびれがひどく、夜も寝られないほどでした。がんが骨に転移して神経を圧迫している。その時は確信を持ってそう思いました。しかし、数日で痛みが引くと、まるで悪夢を見ていて目が覚めたような気分で、転移を確信していた自分が滑稽にすら、思えるのです(ちゃんと受診もしましたが)。
この本の中で、患者である父親は、治療法や退院のことでコロコロと考えを変え、著者を振り回します。しかし、今の僕には父親の気持ちが痛いほど分かるような気がします。人間は、いつも冷静な判断をしているつもりでも、痛みや苦しさがある時と無い時では、全く考え方が変わるのです。
本書は闘病記としてはかなりの長編ですが、読み始めると一気に最後まで読めます(その意味でも著者の書き手としての力量は素晴らしいと思います)。難を言えば、やっぱりこのタイトルはもっと平易なものにした方がよかったと思うのですが、逆に言えば、難しそうなタイトルのことは忘れて手にとって欲しい、読んで欲しい。そう思う一冊です。